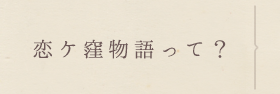偶然のふたり
ゼミは解散。
日頃から高血圧が心配になる程テンションの高い快も、頼みの真衣もいなくなってしまって、葵は気付けば晴樹とふたりきりになっていた。
ここはいったん私もこの場から立ち去って、後日改めて晴樹くんと親睦を深めればいいんじゃないかな、うん、そうしよう。などと算段をつけた葵は、ようやく晴樹の方を向く。彼はぼうっと突っ立っているように見えた。
「私もそろそろ帰ろうかな。晴樹くんは?」
「…俺も帰る」
相も変わらず簡潔な返事。それが気まずいのでひとりで帰ろうとしたのに、葵の作戦は失敗に終わってしまった。彼はこの後用事があるって言ってたんじゃなかったっけ? 葵はそう思って首を傾げた。おまけにいつもは自転車で通学なのだから、そう断ってひとりで帰ることもできたはずなのに、今日はあいにくの雨だ。駅まで一緒に歩いて行かなくてはいけないらしい。
ますますついてない。
「じゃ、じゃあ駅まで一緒だね!」
「うん」
努めて明るく言えば、彼は一応頷いてくれた。初対面ということもあり、帰り道の話題に困ることはなかったけれど、その話題を提供しているのは葵ばかりだ。それでも沈黙よりはマシ。そう思って、葵は一生懸命話しかけた。ちょっと暖簾(のれん)を相手にしているような気分。
「実家暮らしなの?」
「そう」
問いかけには応じてくれるらしい。それだけはほっとした思いで、葵はどうせならと気になることを全部聞いてみることにする。
「あ、じゃあ学校までの通学は時間かかるでしょ」
そう言った葵に、晴樹はかぶりを振った。
「いや。近いから、いつもは自転車だよ」
ああ、それじゃあ私と同じだ、なんて思いながら、葵は話を続ける。
「そうなんだ! 実家はどの辺?」
「恋ヶ窪ってとこ」
正直なところ、葵はかなり驚いていた。何を隠そう、葵の家はまさにその恋ヶ窪なのだ。
「うそー!? 私と一緒!」
私はひとり暮らしだけどね。これはいらない情報かもしれないなあと頭の端っこで思いながらも、葵は勢いのままに付け加えていた。そのくらいびっくりしたのだ。たまたま後から同じゼミに入ってきた相手が実はご近所さんだなんて、なかなかある話ではない。(あ、住んでる駅が同じってことは…、うそ! せいぜい国分寺駅までだと思ってたのに、電車も一緒、しかも降りる駅までおんなじ恋ヶ窪じゃない!)
恋ヶ窪までは西武国分寺線を使うが、目的地が同じ恋ヶ窪なのだから、もちろん一緒に電車に揺られることになる。駅に着けばこの微妙な空気から解放されると思っていたのに、とんだ誤算だ。
予想外の事態にうろたえていたせいか、葵は自分でも良く分からないまま思い付いたことを口走っていた。
「すごい。恋ヶ窪って、名前がすごく可愛いよね。そんなところで育ったなんて、何だかうらやましいなあ…」
なぜ急に恋ヶ窪の名前なんか褒め始めたのか。いや可愛いと思っているのは事実だけれど、葵はそう聞かれたら間違いなく答えられないだろう。ごまかすようにあははと笑って晴樹を見たが、彼は相変わらず無表情だ。おまけにその表情のままこちらを見てくるので、視線が痛いったらない。
だいたい自分の生まれ育ったところなのだから晴樹だってもう少し頷くなりなんなりすればいいのにと葵は思ったのだけれど、彼は葵の気持ちを知ってか知らずか、素知らぬ顔をして半歩前を歩いている。
結局空回りしちゃうんだから、もう無駄に気を使うのはやめにしよう。葵は自然に会話が生まれるまでゆったりと構えることにした。
すると帰り道の先、左手に深緑が見えてきた。国分寺の名所のひとつ、“殿ヶ谷戸公園”だ。秋になると紅葉がとても綺麗だけれど、葵は今の時期の青々と濃い緑色も好きだ。久しぶりの雨で思いきり水を吸って、緑が光って見えるようだった。
葵は大きく深呼吸してみる。森の中のような、良いものがたっぷりつまった空気が体に染み渡るみたいだ。隣を見ると晴樹がじっと公園の緑を見ていた。彼も葵と同じように深呼吸している。
「…寄っていこうか?」
「あ、いや…、今日は」
用事があるんだっけ。そう問えば、晴樹は頷いた。
結局公園には入らずに、葵は晴樹と共に駅の改札を通る。ホームで電車を待つ間は、不思議とほんの少し居心地が良くなった気がした。
ほんの少しだけ。
- 前のお話し
-
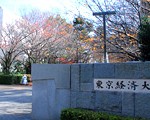 恋ケ窪物語vol.02
恋ケ窪物語vol.02
静かな写真家
text by 依田
2014年01月27日